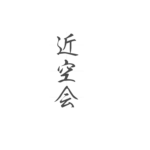練習風景・内容を記載します
■練習会の回数週に1回行っています。
■練習時間
全員合同で2時間行っています。
■参加者
少年部を主体に、一般部・シニアの方々が参加されています。
■正面に礼
練習の最初と最後に全員正座で行います。
■練習内容
①準備運動 ストレッチ体操
②軽運動 ランニング、ハーフスクワット、タイミングゲーム等
③その場基本 正拳突き、逆突き、前蹴りなど
※ 正確に覚えてもらう
④移動基本 前屈立ち、後屈立ち、騎馬立ちからの攻撃技、受け技、蹴り技を
行う。
※ 3本、5本の移動を畳み掛けるように行う
※ 最後に、騎馬立ちによる波返しを行う
⑤約束組手
● 三本組手
● 一本組手(前屈立ちより)
● 一本組手(自由構えより)
● 返しの一本組手(自由構えより)
※ 身構えと気構えを学びます。
※ 残心、作法、読みを学びます
⑥ミット練習 目的は、実際に技を当てることです。
● 突き技、蹴り技の単発練習
● 突き技の連続攻撃、蹴り技の連続攻撃
● 突き技と蹴り技の連続攻撃
● ミットの持ち手が移動しながら行う方法等
いろいろな方法でミット練習を行います。
※ ミットの裏側を攻撃するつもりで行う
※ 力いっぱい、攻撃することが大事です
⑦自由組手
大会参加や組手競技では「実際には技を当てない」ルールです。そういった期間中は当てない練習を行っておりますが、大会の無いこの期間(冬季)は実際に技を当てるルールで自由組手を行っています。
ルールは会長が約30年前に考案した「安全防具付きコンタクトルール」です。ルールを簡単に説明しますと防具を着用した状態で「技を当てても良い」というルールです。当てないルールとは間合いも違いますし、最初はなかなか戸惑いがあって会員のみなさんも苦労しています。
空手にはいろいろな要素がありますが、その中の一つとして実際に技を当てるこのルールは意義があると考えます。このルールでは、下突き、手刀打ち、ローキック等の普段使わない技も使用できるので良いと思います。
このルールにより、自由組手の説明指導が大変容易になりました。実際に技を当てることにより、多くの矛盾が解消されました。当道場では、このルールを発展させていきたいと思います。
※ 対戦相手について
相手の力量により、攻撃の対応を制限する方法を採用
(1) 初級者対上級者では、上級者は受け技のみで対応する
(2) 中級者対上級者では、上級者は受け技、突き技で対応する
(3) その他
※ このルールによる組手練習では、皆さん楽しそうです!
楽しく空手に親しむ、そんな雰囲気に道場が盛り上がります。これからも明るく、楽しく空手を続けましょう。
⑧形(かた) 当道場では松涛館流の形を行っています。
大会がまだ先なので、松涛館流の基本の形の習得に汗を流しております。平安初段から五段までは正確に覚えてもらいます。特にシニア部(65歳以上の方)の皆さんには是非平安の形を習得していただきたいと思います。平安の形は今年から空手を始めた子どもたちに大変良い目標として存在感があります。
上級者の皆さんにおいては、鉄騎初段、慈恩、観空、抜塞、燕飛等の形に、年心に取り組んでいます。また、岩鶴、壮鎮、明鏡、五十四歩(小)の修練に励んでいる黒帯のみなさんもいます。
⑨清掃 練習会の最後は、練習場所の清掃です。昔のような雑巾掛けはしませんが、きれいな清掃と思います。子どもたちの楽しそうなモップがけを見ているとつい嬉しくなります。
⑩モットー 明るく、楽しく空手を学び強くなろう!
写真ギャラリー

-150x150.jpeg)